こんなに面白いなら、もっと早く読めばよかったです!
「スティーブ・ジョブズ I・II」(ウォルター・アイザックソン氏著、井口耕二氏訳、講談社、2012年11月初版)
今更ながらに読みました。既にティム・クックの本も既に出ているというのに。
ジョブズという人、アップルという会社、各プロダクツに込められた思い・歴史、創り出すということ、イノベーション、デザイン、ブランディング、マーケティング、スタートアップ、経営、リーダーシップ、生き方、人間関係、などなど、数えきれないほど多くのことを学べます。そして、面白く生きていくための知恵が沢山詰まっています。
ジョブズの人生と彼が成し遂げたことを知ることは、コンピュータが登場してから現在までのテクノロジー革命の歴史と社会の大きな変化を知ることそのもので、歴史的な文献としても価値のある本と思いました。コンピュータ、映画、音楽など、様々な業界に地殻変動が起きる瞬間を目撃するような体験でした。ジョブズとゲイツの関係性、ジョブズがディズニーやU2など業界を超えて組んでいくところなども、とても面白かったです。
(以下、引用ページは、Iは文庫本、IIは日本語版ペーパーバック版のページ数です。)
ジョブス本人が「本書に口は挟まない、(中略)あらかじめ見せてもらう必要もない」(I, p.14)と決めた通り、彼の好ましい面もどうしようもない面も両方が描かれており、(もちろんジョブズに対する愛が本を通じて流れていますけれども)伝記にありがちな英雄を讃える内容になっていません。
なので、とても人間味が感じられ、生身のジョブズという人物が浮かび上がりますし、同時に、この人の凄さ・奇才ぶりがより際立ちます。
(末尾の方で、ジョブズ自身が実は「このプロジェクトはものすごく怖かった」と白状しています。II, p.451)
詳しい内容は本を読んで頂くとして、ここでは私がこの本から感じたことを、メモしておきたいと思います。教科書や道徳的観念に反するものもあるのかもしれないですが。
超大作で、感じるものも膨大。2回に分けて書きます。
今回は、ジョブズの仕事の仕方について。
- まず、ビジョン。その内容が非現実的なら、それがどうしたら実現できるかを考える。
- Aクラスの人間だけを集めて何が悪い。
- ビジョンのもとには、垣根は存在しない
- 全ユーザー体験に責任を持ちたい
- 前言撤回で何が悪い。
- 創造するということについて
- 儲けたお金は、ミッションのために使うもの。
- リアクティブからやることは、たいていうまくいかない。クリエイティブからやることは、困難を乗り越える。
まず、ビジョン。その内容が非現実的なら、それがどうしたら実現できるかを考える。
もっとも簡単にジョブズの逆鱗に触れる方法は、できない理由をあげつらうこと、でしょう。
そんなことは彼は聞きたくない。
美や革新を追求せず、これまでの経験できることの積み上げでしかない新製品なんて意味がない。
ジョブズが常に目指していたのは、「素晴らしい製品をつくること」「すごい製品をつくること」。
「すばらしいデザインとシンプルな機能を高価ではない製品で実現できたらいいなと思ってきた。それこそ、アップルがスタートしたときのビジョンだ。それこそ、初代マックで実現しようとしたことだ。それこそiPodで実現したことなんだ」(I, p.46)
そして、そのためのプロセスは、
「自分たちにこんな技術があるから、こんなものをつくろう。」ではありません。
「こんなものがつくりたい。こんなものが欲しい。どうすればできるだろう。」です。
「顧客が望むモノを提供しろ」という人もいる。僕の考え方は違う。顧客が今後、なにを望むようになるのか、それを顧客本人よりも早くつかむのが僕らの仕事なんだ。ヘンリー・フォードも似たようなことを言ったらしい。「なにが欲しいかと顧客にたずねていたら、『足が速い馬』と言われたはずだ」って。欲しいモノを見せて上げなければ、みんな、それが欲しいなんてわからないんだ。だから僕は市場調査に頼らない。歴史のページにまだ書かれていないことを読み取るのが僕らの仕事なんだ。(II, p.468)
というのは有名な彼の言葉。
また、こちらは、ゼロックス社のパロアルト研究所(PARC)のビジョナリーな研究員アラン・ケイの言葉で、ジョブズのお気に入りの言葉。
「未来を予測する最良の方法は、自分で作り上げることだ」(I, p. 206)
このあたり、最近行ったロバート・フリッツ氏の講演で聞いた緊張構造の話ととても符合します。(これから読む本:「偉大な組織の最小抵抗経路 リーダーのための組織デザイン法則」)
「どうすればできるだろう」は徹底的に考え、議論し、試す。
そのためには、寝食を忘れて没頭するし、周囲にもそれを求める。
ワークライフバランスとか、働き方改革など主張していては、うん、わかった、じゃあアップルは君の働く場所じゃないね、となったでしょう。少なくともジョブズの時代は。
アップルで製品をつくることは、ほとんどアート作品をつくることと同じ。
一人の芸術家と同等以上のこだわりを、企業で実現していきます。
自分自身が、全身から知恵を絞り出すのは当然として、周囲にも限界の突破を求めます。
デザイン部門のトップ、ジョニー・アイブとジョブズが組んでクリエイティブ面を進めるようになった1997年以降、ふたりとも、エンジニアの懸念はできない理由を並べているだけで、それを乗り越えさせなければならないと考えるようになった。すごいデザインは神業のエンジニアリングを引き出すとふたりは信じていたし、iMacやiPodの成功により、その信条は正しいと証明された。
エンジニアから無理だと言われたこともとにかくやらせている。だいたいはそれでうまくゆくのだ。(II, p.389-390)
これは、エンジニアに対する例ですが、広告も、デザインも、どの部門でも同じ。
なぜそれができるのか。
一つには、「素晴らしい製品をつくる」共通のビジョンに皆がコミットしているから。
もう一つには、アップルの場合、そんなの無理・・・と弱音を吐いたり反論しても、ジョブズの特技「現実歪曲フィールド(Reality Distortion Field, RDF)」に捉えられると、なぜかきっとできると信じてやり始めることになるようです。
ありありとビジョンを持って語られる、君にはできると言われる。
そうすると、不思議なもので、「そうだ、できる、我々はできるぞ!」と思い込んでしまう。
人たらし、と批判することは簡単ですが、これは「人を動かす」という観点では、侮れないことのように思います。人は気持ちで動くもの。気持ち次第で越えられなかった壁を越えることはままあります。
現実には越えられなかったとしても、だから何だというのでしょう。「騙された」と言う人もいるかもしれません。それが何なのでしょう。
騙されずにいれば、無駄な仕事はしないで済む。
一方で、騙されてやってみて進んだ道の後には、目指していた理想形が完成していなくても、何かが生み出されているのではないでしょうか。それは後々、思いもよらぬところで使えるものかもしれません。
ジョブズがさんざんひどい目に遭わせた何十人もの同僚に話を聞いたが、彼のおかげで、それまでできると考えもしなかったことができたと、皆、判で押したように、悲惨な体験談を締めくくるのだ。(II, p.464、筆者)
それは社員だけではなく、取引先にも及んでいます。
「ジョブズとアップルのおかげで当社は成長しました。我々は、一人ひとり、自分たちが作る製品に夢中なのです」(II, p. 314、iPhone用の強化ガラス=ゴリラガラスを開発したコーニンググラス社のウィークスCEOの言葉)
ジョブズは、そのやり方が絶対素晴らしいとは言えないけれども、確かに人の能力を開花させた人だと思います。
そして、もしかしたら、私たちは皆、自分たちの能力を開花させてもらう瞬間を待っているのかもしれません。
Aクラスの人間だけを集めて何が悪い。
ですから、ジョブズのもとには、自分の能力をもっと開花させたいという人たちが集まってきます。
ジョブズも、そういう人たちを求めています。
逆にいうと、自分たちのビジョンに共感し心身ともにコミットするのでなければ、そんな人間にはいて欲しくない。
「チームが成長するとき、多少ならBクラスのプレイヤーがいてもいいと思ってしまうが、そうするとそいつらがまたBクラスを呼び込み、気づいたらCクラスまでいる状態になってしまう。Aクラスのプレイヤーは同じAクラスとしか仕事をしたがらない、だからBクラスを甘やかすわけにはいかない・・・そう、僕はマッキントッシュの体験から学んだんだ」(I, p.367-368)
ここまで言い切られると、もはや何だか気持ちが良いなとすら思います。
「どんな人でも受け入れなくては」などという罪悪感は、かけらも感じられません。
なお、これ、多様性がないということではありません。
むしろ、逆です。「すごいものをつくりたい」と言う信念を共有した、多様な能力や性格を持つ人の集まるチームになります。様々な分野からトップクラスの人間だけが集まる。そこは、世界で最も贅沢な多様性を享受する世界と思います。
同じビジョンを持つ、自分が尊敬する人たちと仕事をすることは、興奮し、満たされる体験であり、この快感を体感すると、きっとやみつきになると思います。
ビジョンのもとには、垣根は存在しない
すばらしい製品を完璧に作りたい。
そのために必要なことは、躊躇なく、全てやる。
そういうマインドの前には、垣根や境界は存在しません。
会うべき人には、どこまででも会いに行く。
それは、ジョブズの世界を際限なく広くし、そこにまた新しい化学反応が起きて、誰も想像しなかったようなものが生まれます。
ミニマリズムを信奉する中で和のスタイルに惹かれて、イッセイ・ミヤケやイオ・ミン・ペイとも交流する。(余談。その親交から、ジョブズのトレードマークになる黒いハイネックは、イッセイ・ミヤケから100枚プレゼントされたもの。)
美的なものを求めて、禅と出会う。京都にも何度も飛ぶ。
アートとテクノロジーの交差点を求めていたら、ルーカス・フィルムにたどり着く。
iPodとiTunesのために、音楽レーベルのトップたちと交渉する、U2とコラボレーションをする、ビートルズのより良い写真を求めてオノ・ヨーコにも接触する。
ジョブズが会いに来てくれた各業界の人たちも、この異なるものの出会いをきっと楽しんだでしょう。
全ユーザー体験に責任を持ちたい
完璧につくったものは、完璧に届けたい。完璧さをユーザーに体験してもらいたい。誰にも邪魔して欲しくない。
アップル製品が他の製品と互換性が低いまたはないことは、かつて不便に感じていたことの一つなのですが、なぜそうなのかが、本書を読んでよくわかりました。(もう今はMS Officeなども動くので、あまり困ることはなくなりました。)
アップルのクローズドな感じは、ビジネス上の戦略という観点もあるものの、原点としては、この美的世界を他者によって崩されることは許さないというポリシーによるものなのだと。
パッケージへのこだわりも、アップルストアを作ることも、PCが開けられなくなっていることも、アップルケアなどでユーザーサポートが手厚いことも、すべて繋がっているのだと。
前言撤回で何が悪い。
「リーダーはブレてはいけない。」よく言われることです。
確かにそうだと思います。
が、ブレるべきでないのは信念や価値観(what)であって、その信念をどう現実化し、表現するか(how)については、むしろ、固執の方が危険と思います。一度決めたhowであっても、whatが正しく表現されていないのであれば、それはやり直しが必要な時でしょう。
ジョブズはこの点もextreme。「トイ・ストーリー」(PIXERにて)、アップルストアなど、最後の最後まで、自分たちの表現しようとしていることが表現されているか、伝わるかを確認し、完成まであと少しと言うところでプロジェクトを変更したりしています。本書の中での極めつけは、iPhoneのデザイン変更でしょうか。9ヶ月かけてやってきたことにリセットボタンを押しています。
これは、普通であれば、リーダーにとって、ものすごく勇気のいること。
チームメンバーにとっては、肉体的にも精神的にもしんどいこと。
それについてこれる人たち、この完璧主義を理解できる人たちだけが、ジョブズとともにやっていけます。
それはまるで、アーティストが彫刻や楽曲を生み出す過程、職人がプロフェッショナルとして自分の仕事をする時と同じです。満足いくものができるまで、何度でもやり直す。そういうところからexcellenceが生まれます。
実際、つくりだすということにおいて、ビジネスもアートも本来は変わらないはず。
ジョブズとアップルがすごいのは、これが小さなベンチャーの時だけではなく、大企業になってもその文化が続いているところです。
ジョブズは、大企業になっても創造性とイノベーションが失われず長く続くヒューレット・パッカードやウォルト・ディズニー・カンパニーを尊敬し、自分もそういう会社を作りたいと願い、実際にそれをつくりあげました。
「いつまでも続く会社を作ることに情熱を燃やしてきた。すごい製品を作りたいと社員が猛烈に頑張る会社を。それ以外はすべて副次的だ。」(II, p.467)
創造するということについて
ジョブズは常に、つくり出すことに価値を置いています。
そのつくり出すプロセスは決して直線的ではなく、また、決して一人の人間の中から生まれているものでもありません。
だからこそ、議論が大事。プレゼンテーションは議論のきっかけづくりに過ぎず、用意されたストーリーを最後まで黙って聞いているものではありません。
「スティーブは話し合って考えていくその瞬間が大好きなんです。『スライドが必要なのは、自分の話していることがわかっていない証拠だ』と言われたこともあります」(II, p.171、iPod開発チームを率いたトニー・ファデルの言葉)
人との出会い、偶然との出会いこそ、創造の貴重なリソースです。
「ネットワーク時代になり、電子メールやiChatでアイディアが生み出せると思われがちだ。そんなばかな話はない。創造性は何気ない会話から、行きあたりばったりの議論から生まれる。たまたま出会った人になにをしているのかたずね、うわ、それはすごいと思えば、いろいろなアイディアが湧いてくるのさ。」(II, p.247、ジョブズの言葉)
また、創造するということは、既存のものの存在価値を失わせたり、壊したりする可能性もあるものです。たとえ、その既存のものが、かつて自分自身がつくり出したものであっても。
(前略)ジョブズは”共食いを怖れるな”を事業の基本原則としている。
「自分で自分を食わなければ、誰かに食われるだけだからね」
だから、iPhoneを出せばiPodの売り上げが落ちるかもしれない、iPadを出せばノートブックの売り上げが落ちるかもしれないと思っても、ためらわずに突き進むのだ。(II, p.207)
目の前にあるものは全て、つくりだすためのリソース。
自ら過去を壊してでも、新しいものを生み出す。
こういう姿勢からも、ジョブズが、利益追求ではなく、本当に創造することを最上位においていたことが伺えます。
儲けたお金は、ミッションのために使うもの。
一方で、ジョブズは、儲けのアップル社及び自分自身の利益の取り分についてはシビアです。提携先の企業相手にも、経営陣相手にも、しっかり交渉します。
IPOやストックオプションでがっぽり儲けています。
けれども、
「クルーザーを買うこともないからね。お金のためにやっているわけじゃない。」(I p.568)
家を豪華にしたりセキュリティを強化したり、慈善事業に使うものでもありません。
では、何のために?
それは、もっと自由にアイディアを形にするためのもの。「すごい製品を作る」というミッションのためのもの。
自分たちが望むクオリティで、自分たちが望むものをつくろうとすれば、障害になるものも出てくる。その時にお金は力を持つ。「お金」というものについて、ジョブズはきっと「自分たちを自由にするもの」と見ていたのではないかと思います。
ピクサーのIPOも、その資金を持つことで、ディズニーの資金に頼らずに映画を作れるようになることにとても意味があった(I. p.568)
(前略)利益を上げるのもすごいことだよ?利益があればこそ、すごい製品を作っていられるのだから。でも、原動力は製品であって利益じゃない。スカリーはこれをひっくりかえして、金儲けを目的にしてしまった。ほとんど違わないというくらいの小さな違いだけど、これがすべてを変えてしまうんだー誰を雇うのか、誰を昇進させるのか、会議で何を話し合うのか、などをね。(II, p.467)
大金を稼いだら、使い方も大胆。デザインや効果的な広告など、自分が大事と思うものには、惜しみなく、目が飛び出るような額を注ぎ込みます。
自家用機などは買うけれども、それは、贅沢をしたいということよりも、より良いものを産み出すために、もっとフレキシブルに制限なくスピーディに動きたいというように見えます。
リアクティブからやることは、たいていうまくいかない。クリエイティブからやることは、困難を乗り越える。
成功の裏には、沢山の失敗があります。
読んでいて感じたのは、リアクティブな動機からやっていることはだいたいうまくいっていない、クリエイティブな動機からやっているときは素晴らしいものを生み出す結果になっている、ということ。
リアクティブとは「反応的」なこと。
リアクティブなとき、人の行動の動機は、自分の外にあります。何かを成し遂げるのは、誰かに褒められるため、自分の正しさを証明するため、自分の凄さを証明するため。
対するクリエイティブとは「創造的」なこと。
クリエイティブなとき、人の行動の源泉は自分自身です。自分の魂の声が自分を突き動かします。誰かかが自分のことをどう言うかは、もはや大した問題ではありません。この行動の結果、賞賛や大きな成果が得られたとしても、それは副次的なものです。
(詳しくは、「なぜ人と組織は変われないのか――ハーバード流 自己変革の理論と実践」(ロバート・キーガン氏著)、ザ・リーダーシップ・サークルご参照。)
ジョブズのリアクティブの極みはNEXTと思います。自分がアップルから追い出されたと感じたジョブズが、アップルから人を引き抜き、立ち上げた会社。その開発は、アップルへの対抗心と裏切り者の経営陣への怨念以外の何物でもないように見えます。結果として、空回りして、うまくいかない。
対して、純粋に、一般の人にも親しみやすいコンピュータをという想いから生まれたアップルII、テクノロジーとアートの融合に魅せられたPIXERのアニメーション、自分たちが欲しい音楽プレーヤーが欲しいという意欲から生まれるiPodなど、本当に自分が大事にしていること、本当にこの世に創り出したいものに純粋に心血を注いでいるときに、時代をシフトさせるような革命的な製品が作られています。
ジョブズ自身の言葉でもこれが感じられます。
僕は、年を取るほど、モチベーションが大事だと思うようになった。(中略)アップルが勝ったのは、僕ら一人ひとりが音楽を大好きだったから。みんな、iPodを自分のために作ったんだ。自分のため、あるいは自分の友達や家族のために努力するなら、適当をかましたりしない。大好きじゃなければ、もう少しだけがんばるなんてできない。もう1週間とがんばれやしない。音楽を大好きな人と同じだけ、現状をなんとかしようと努力なんてできないんだ。(II, p.206)
「自分たちが使いたいと思う電話を作ろう」と盛り上がった。「あれほどやる気が出る目的はちょっとないね」(II, p.304)
モチベーションの大事さは、経営でもよく言われるところ。
報酬や賞賛を得るためのモチベーションは長続きせず、自分の信念や大好きなことのためのモチベーションこそが、苦難を乗り越える原動力になります。
これまで、単純に、スタイリッシュだから、持っていると何となく嬉しいから、使いやすいからという理由でアップル製品を使うようになっていましたが、この本を通じて、それぞれの製品について、これだけの試行錯誤と限界を超えた挑戦があることを知り、更に愛着がわきました。
また、この私が感じている、アップル製品を買うところからのユーザー体験すべて自体がまさにジョブズのこだわりそのものなのだと知ると、完全に術中にはまっていたんだという、ちょっとこそばゆい気持ちにもなります。
さて、すでに10,000字。続きは(2)で。ジョブズの人となりに焦点を移したいと思います。
ジョブズ、高校時代にお気に入りの本:

- 作者: ウィリアムシェイクスピア,William Shakespeare,福田恆存
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1967/11/28
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 23回
- この商品を含むブログ (34件) を見る
ジョブズ、リード・カレッジ時代&中退後に感銘を受けた本:

- 作者: リチャード・モーリスバック,Richard Maurice Bucke,尾本憲昭
- 出版社/メーカー: ナチュラルスピリット
- 発売日: 2004/02/01
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る

小さな惑星の緑の食卓―現代人のライフ・スタイルをかえる新食物読本
- 作者: フランシス・ムア・ラッペ,Frances Moore Lappe,奥沢喜久栄
- 出版社/メーカー: 講談社
- 発売日: 1982/05
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
有名なスタンフォードでのスピーチの締めの言葉「Stay Hungry, Stay Foolish」はこの雑誌の最終号の裏表紙から。「iPadはデジタル版『ホールアースカタログ』ー創造性が生活の道具と出会う場」(II, p.350)
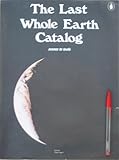
The Last "Whole Earth" Catalogue
- 作者: Portola Institute
- 出版社/メーカー: Penguin Books Ltd
- 発売日: 1972/10/26
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログを見る
ジョブズ、愛した音楽:

アビイ・ロード【50周年記念2CDエディション】(期間限定盤)(2SHM-CD)
- アーティスト: ザ・ビートルズ
- 出版社/メーカー: Universal Music =music=
- 発売日: 2019/09/27
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
ジョブズが尊敬していた会社①:ヒューレット・パッカード
ジョブズが尊敬していた会社②:ウォルト・ディズニー・カンパニー
デザインの着想:アイクラー・ホームズ
マッキントッシュCM「1984年が『1984年』のようにならない理由」の着想:
![一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫) 一九八四年[新訳版] (ハヤカワepi文庫)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41ZAgdWin2L._SL160_.jpg)
- 作者: ジョージ・オーウェル,高橋和久
- 出版社/メーカー: 早川書房
- 発売日: 2009/07/18
- メディア: ペーパーバック
- 購入: 38人 クリック: 329回
- この商品を含むブログ (350件) を見る
実の妹モナ・シンプソンの著書








